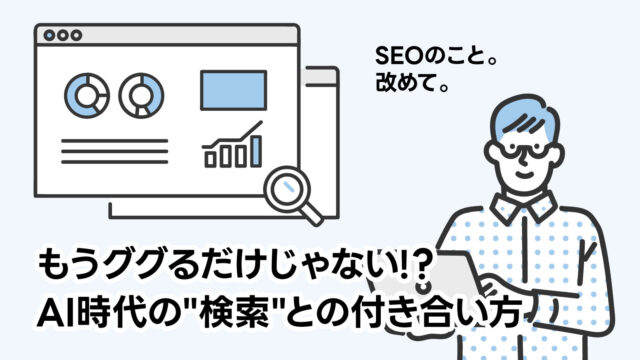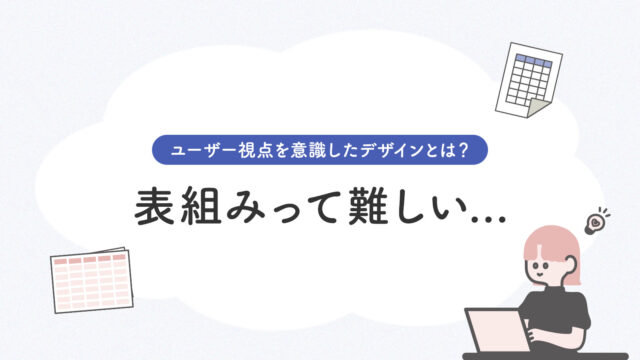2023.10.04#SEOのこと
SEOのこと。改めて。検索エンジン、Googleの仕組みについて
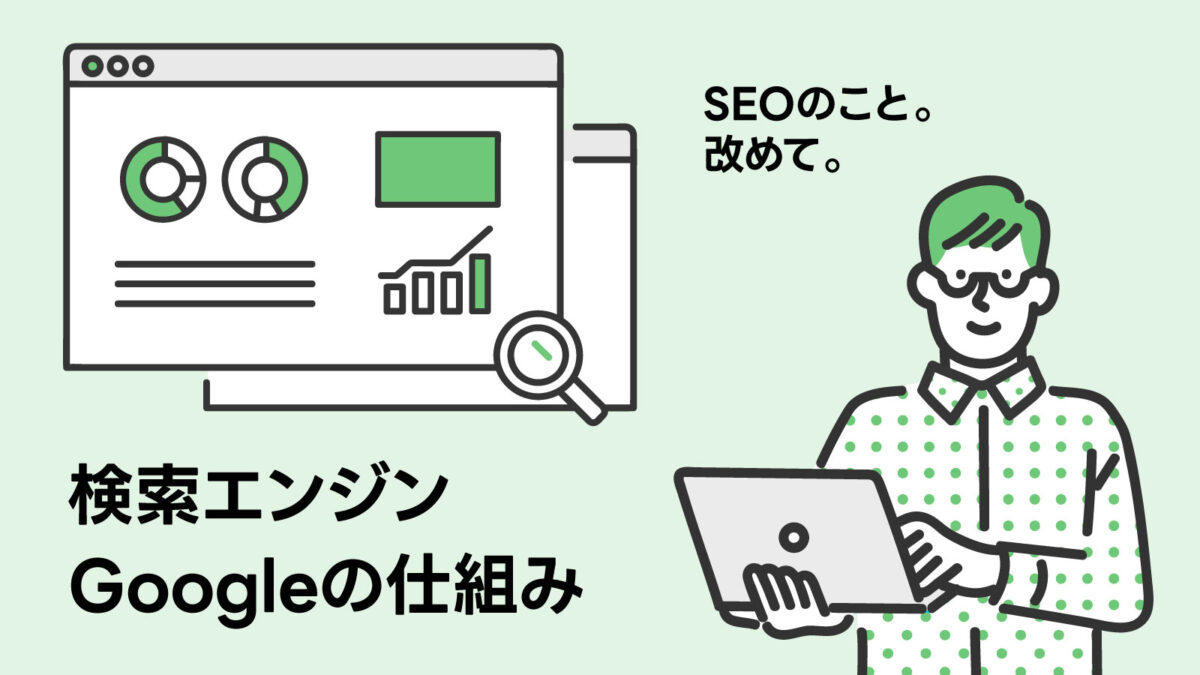
こんにちは。タナカラの中村です。
ちょっと時間が経ってしまいましたが、SEOのこと。改めて。2回目。
今回は、Googleの検索結果を表示する仕組みについてです。
結論:わかりません!
いきなり身も蓋もない結論からになってしまいますが、仕組みなんてわからないんです。
わかってたら苦労しません。
200以上の項目を判定しているそうで、その基準は常に変化・アップデートを繰り返し、アルゴリズムは当然、非公開。
対策できるわけがありません。
ですが、ガイドラインは公開されています。(案外、Googleって優しい?)
https://www.google.com/search/howsearchworks/how-search-works/ranking-results/
主な要因は次の5つ。
- 検索クエリの意味
検索クエリとは、検索に使用した単語やキーワード、それらの組み合わせのこと。
ここからユーザーの検索意図を把握して、適切な結果を表示する。 - コンテンツの関連性
検索クエリに関連する情報が含まれているページ(ウェブサイト)を表示する。
ページタイトルや見出しに検索クエリが含まれていれば、関連があると評価されるが、その数(掲載回数)が多ければ関連性が高いと評価されるわけでもない。 - コンテンツの質
関連性のあるページの中から、コンテンツの質が高いものを表示する。
質を見極める要因の一つは被リンク。他のサイト(著名なサイトなら尚よし)からたくさんリンクされているページの方が信頼性が高いと評価される。 - ウェブサイトのユーザビリティ
使いやすいウェブサイトであることも重要。
検索クエリと関連性があり、コンテンツの質が高くても、使い勝手が悪い場合は評価が下がる。
代表的な例は、表示するまでに時間がかかる重いページ。 - コンテキストと設定
ユーザーの状況に合わせた結果を表示する。
例えば場所。住んできる場所や所在地に関連性が高い情報を表示する。
その他、ユーザーの検索設定を考慮する。
かなりの意訳ですが、いかがでしょう?
抽象的ですが、納得できませんか?
作る側、情報を発信する側の視点では、正解がない話になりますが、使う側の視点に立ってみれば、素直にありがたいと思ってしまいます。
すでに検索、そしてその結果から情報を取捨選択するというアクションが当たり前すぎて、そこに何も感じなくなっているような気がしますが、その前段階で、情報はすでにふるいに掛けられています。
Googleだって使ってもらえないと困る
話を戻します。
Googleの検索結果表示の仕組み(アルゴリズム)は非公開です。
仮に公開した場合、その対策「だけ」をガッツリ取り組んだサイトが上位表示されてしまうことは容易に想像できます。
そして、それが役に立たない情報ばかりだったら、ユーザーからの信頼がなくなり、使ってもらえなくなります。
そうなるとGoogleだって困りますよね、広告収入とかいろいろと。
ユーザーにとって有益な情報を提供する「ユーザーファースト」がGoogleの検索順位決定のベースにある考え(思想)だと言えます。
ですので、Googleの仕組みを知ってハックするなんてことは考えず、素直にいいコンテンツを作ることに注力していきましょう。
次回は、SEOを考えたウェブサイトの作り方についてです。
それではまた。