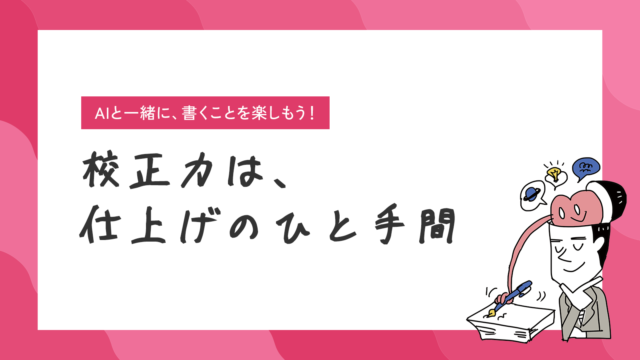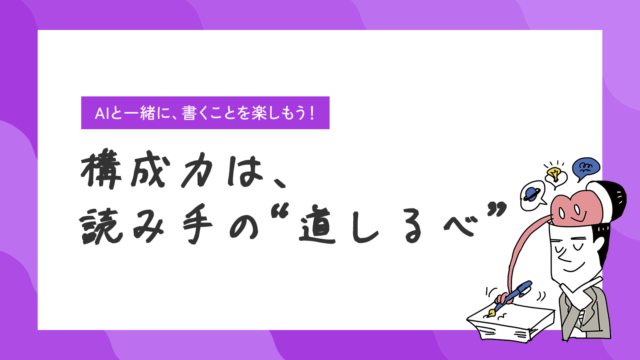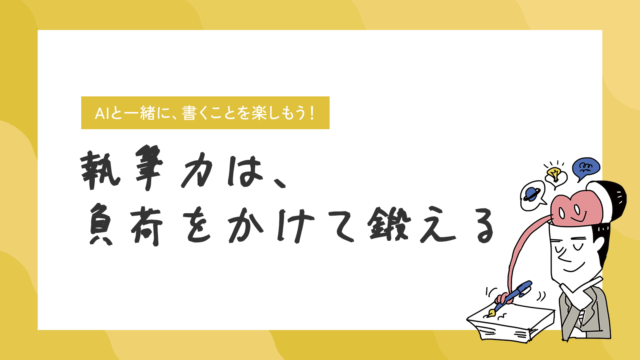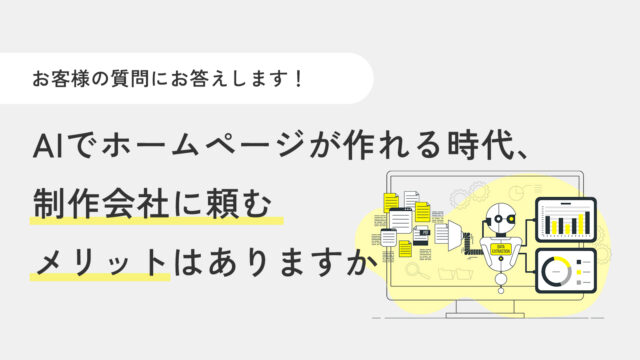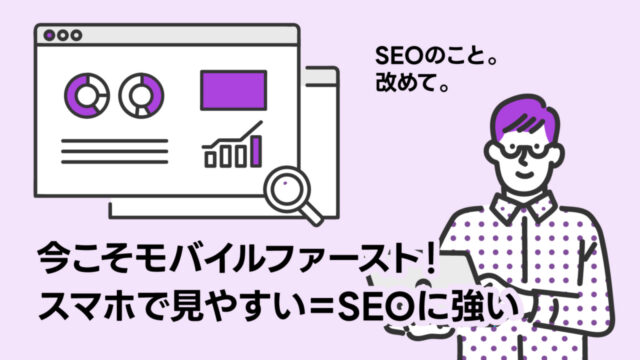2025.07.09 #ライティング
AIと一緒に、書くことを楽しもう!文章力は、3つの力のかけ算
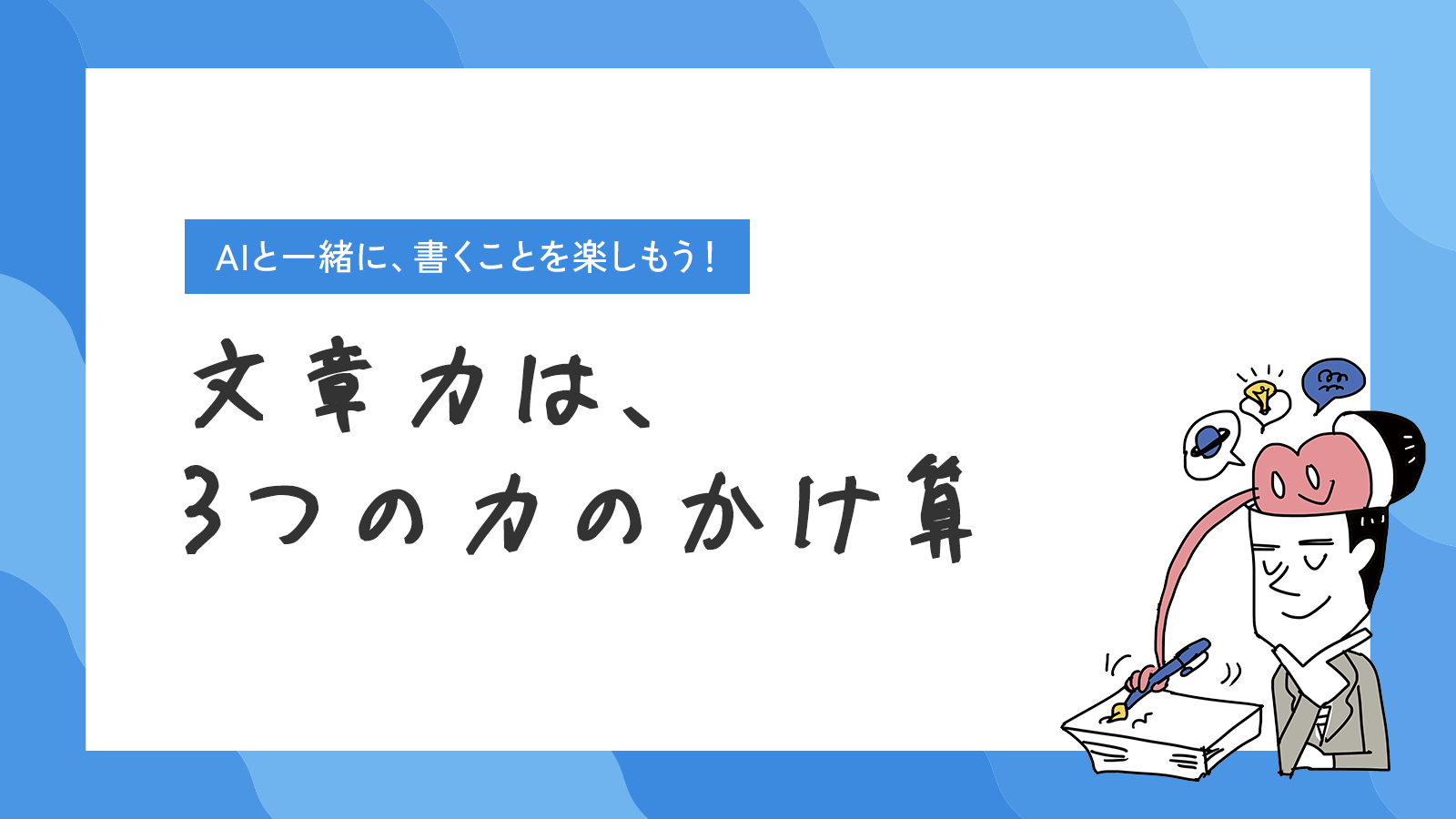
こんにちは!エンジニア・ディレクター・ライターのヤマグチです。
タナカラコラムでも、AIについて触れることが増えてきましたが、皆さんは文章作成にAIを使っていますか?
メールの文章や報告書のたたき台といったテンプレートのアイデアとして使ったり、適切な表現に言い換える案を出してもらったりと、活用している人も多いと思います。
私もライティング業務で、AIを使うことが増えました。
ChatGPTが出始めた当初は「こういう指示をしたら、どのくらいのものを書いてくれるかな?」と試すような感覚でしたが、今はこちらで指示して、意図したことを伝えれば、概ねちゃんと書き上げてくれます。
便利な世の中になったなー、と思っていたのですが、あるときふと、「AIを使ってばかりいると、自身の文章力が落ちるのでは?」と不安になってきました。
そして、ふと気づいたんです。
「あれ?文章力って、なんだ??」
そんなわけで、これまであまりきちんと言葉にしてこなかった「文章力」について考えてみたいと思います。
文章力って、ひとつじゃない
「文章力」と聞いて、どんな力を思い浮かべますか?
美しい文章を書く力?難しい言葉を使いこなす力?
私はライターという仕事柄、文章力とは“伝えるために言葉を設計する力”だと考えています。
そしてその中には、「執筆力」「構成力」「校正力」という3つの要素があると思っています。
- 執筆力:ゼロから言葉を紡ぐ力
- 構成力:伝える順番・形を組み立てる力
- 校正力:読みやすく、誤解なく整える力
執筆は「言葉を自分の中から生み出す力、自己表現の筋肉」、構成と校正には「整理力・判断力・他者視点」が必要になります。
これが全て備わっていたら文章力が高くて、書くことが苦にならないのかもしれません。
逆に書くことがあまり得意じゃないとか、うまく書けないとか、ちゃんと書いているつもりなのに上司にダメ出しをくらうとか、そういう場合は3つの要素のうち何かか欠けているのかもしれません。
AIは道具ではなくパートナー
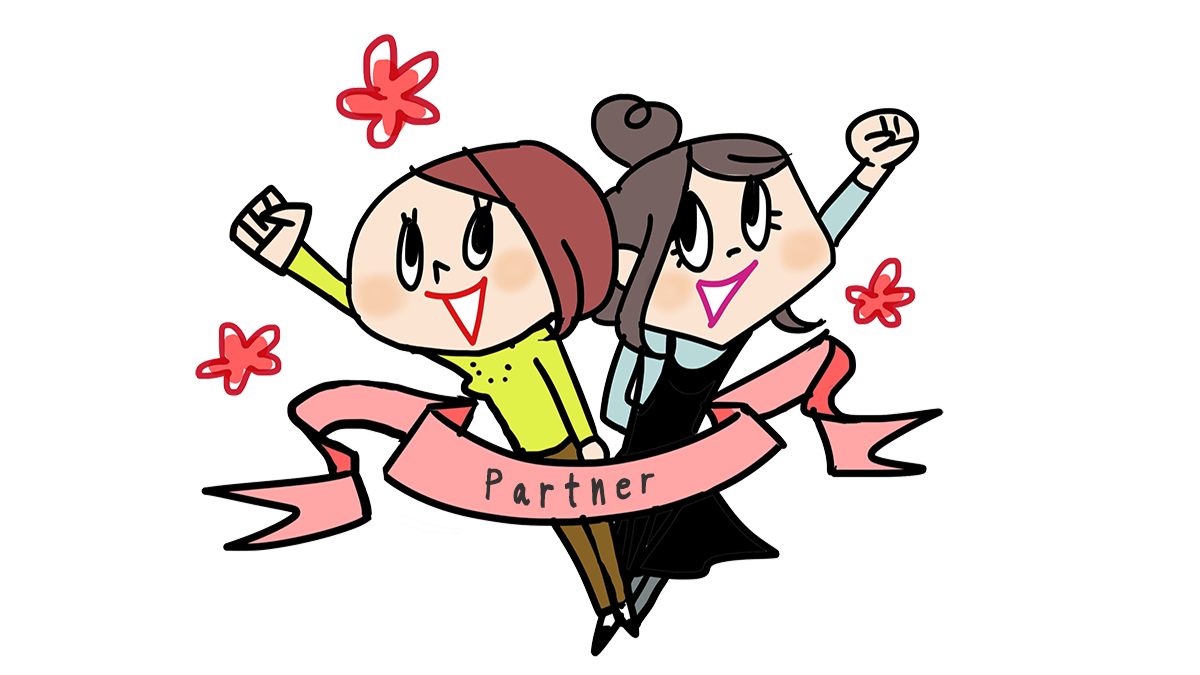 AIをパートナーにしよう!
AIをパートナーにしよう!
AIを「全部自動でやってくれる魔法の道具」と思っていると、期待した答えが返ってこないことがあります。
丸投げするのではなく、原稿のたたき台や構成案、自分が書いた文章の添削など、3つの力のうち、どの力について補助してもらうのかを意識して任せてみる。
それによって、思ったような文章が仕上がるだけではなく、自分自身の「文章力」も鍛えられるような気がします。
AIの台頭で、AIが代わりに書いてくれる…!という世界線がやってくるかもしれませんが、私はAIの力を借りることで、「書くことが苦手」「苦痛」という人が減るのではないかと思うのです。
書くことに悩んだとき、すべてを任せるのではなく、どこか一部を手伝ってもらう。そんなふうに付き合うことで、書くことが楽になる。いや、そこを通り越して、書くことが楽しくなるのではないでしょうか。
そんな希望観測的な思いを抱きつつ、次回は「執筆力」「構成力」「校正力」の3つの力について、それぞれ丁寧に考えてみる予定です。